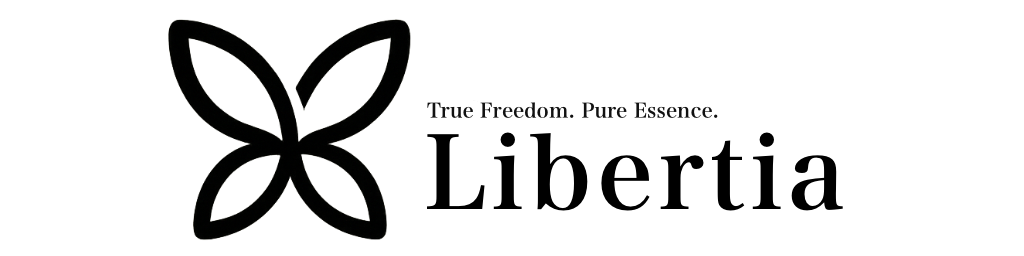不動産売却のよくある質問(FAQ) | 株式会社リベルシア
よくある質問
該当するFAQが見つかりません。キーワードを変えてお試しください。
リベルシアに関すること
- 事務所を持たないとのことですが、本当に安心して取引できますか?
-
はい。
宅地建物取引業の免許を取得するには、取引責任者の設置や法令遵守体制が厳格に求められます。
当社もこれを満たしており、宅建士による重要事項説明や契約書の交付など法定の手続きはすべて通常どおり行います。
事務所にかかる賃料を削減することで、余計な固定費をなくし、お客様により有利な条件を提供しています。 - 借入をせずに経営しているとのことですが、事業拡大に支障はありませんか?
-
当社は基本的に借入に依存しない経営をしています。
これは、固定費を極限まで抑えて、お客様に還元するためです。
ただし、宅地分譲など「合理的に利益が見込めるプロジェクト」については、戦略的に金融機関から借入を行います。
無闇に借入を増やして経営を圧迫するのではなく、攻めるところは攻める、守るところは徹底して守る。
このバランスによって健全かつ持続的な経営を実現しています。 - AIに業務を置き換えていると聞きましたが、人のサポートはきちんとありますか?
-
はい。
契約・重要事項説明・法令遵守といった「人が担わなければならない業務」はすべて代表者である宅地建物取引士が直接行います。
AIは事務作業や情報整理を担うことでコストを下げていますが、最終的な判断や責任はすべて人が負います。 - 利益額まで公開するとのことですが、逆に手抜きやリスクを負わない取引になるのでは?
-
いいえ。
当社が開示する利益額は、契約不適合責任(民法562条)を履行するために必要な「保証資金」です。
土壌汚染や地盤改良の可能性など、不測のリスクに備える合理的な金額です。
つまり、利益を公開することは「手抜きの余地がない」ことを意味し、むしろ安心材料となります。 - 大手不動産会社と比べて小規模ですが、倒産リスクはありませんか?
-
当社は固定費を極限まで抑えているため、経営が圧迫されにくい構造を持っています。
従業員や事務所の維持費がかからないため、取引が一時的に減っても存続に大きな影響を受けません。
また、全ての工程を代表者が一貫して担うことで、責任の所在が明確になっています。 - 取り扱いエリアはどこですか?
-
当社は鳥取県米子市を拠点に、鳥取県西部(米子市・境港市・西伯郡など)から島根県東部(松江市・安来市など)を中心に不動産を取り扱っています。
ただし、この地域に限らず、ご依頼があれば県外の物件についても対応可能です。
地域を限定せず、柔軟に対応いたします。 - 遠方に住んでいますが、相談は可能ですか?
-
はい、可能です。
当社ではオンラインでのご相談を歓迎しています。
以下のようなシステムを活用することで、遠方にお住まいの方でも来店することなく、安心して取引が可能です。・Google Meet等を利用したオンライン面談
・宅建業法に基づく重要事項説明のオンライン実施
・電子契約システムによる契約手続き
取引の基本・契約に関すること
- 不動産の売買や賃貸契約の流れはどうなりますか?
-
一般的な流れは以下のとおりです。
1.物件探し・内覧
2.申込み(買付証明書や入居申込書の提出)
3.契約前の重要事項説明(宅建士による法定説明)
4.契約締結(売買契約書・賃貸借契約書に署名押印)
5.手付金や敷金の支払い
6.引渡し・残代金決済(売買の場合は登記、賃貸の場合は鍵の引渡し)
- 手付金とは何ですか?
-
売買契約時に買主が売主に支払う金銭で、契約成立の証拠金です。
・解約手付としての性質があり、買主は手付金を放棄して契約を解除できます。
売主は受け取った倍額を返還して解除できます(民法557条)。・相場は売買代金の5〜10%程度です。
- 仲介手数料はいつ、いくら払うのですか?
-
仲介会社に支払う報酬で、宅建業法で上限が定められています。
・売買:取引価格が400万円超の場合、上限は「売買価格×3%+6万円+消費税」
・賃貸:原則は「家賃1か月分以内」
- 売買契約後に物件に欠陥が見つかった場合は?
-
2020年の民法改正以降、売主は「契約不適合責任」を負います。
・契約内容に適合しない場合、買主は修補・代替物引渡し・損害賠償などを請求できます。
・特約で責任範囲を限定することは可能ですが、宅建業者が売主の場合は消費者保護の観点から厳しく制限されています。
- 契約を解除できる場合はありますか?
-
代表的な解除のケースは以下の通りです。
・手付解除:手付金放棄または倍返しで解除(契約後、履行に着手するまで)
・ローン特約解除:住宅ローンが不成立の場合に解除できる
・合意解除:当事者の合意による解除
・違約解除:契約違反がある場合に解除(違約金発生の可能性あり)
法令・制度に関すること
- 自分の土地を分けて売ると、宅建業法に違反することがありますか?
-
はい。
「自分の土地だから自由に分けて売れる」と思われがちですが、一定規模を分譲して複数の取引を行えば、宅建業としての規制対象になります。
心配な場合は、宅建業者や行政に確認を取ると良いでしょう。・宅建業(宅地建物取引業)とは?
宅建業法第2条で定義されており、「宅地や建物の売買・交換・賃貸を業として行うこと」をいいます。
ここでいう「業として」とは、反復継続して利益を得る目的で行う場合を指します。・一度だけ売る場合
自宅や相続した土地を1回だけ売却するのは「業」ではないので宅建業にあたりません。・大きな土地を分割して売る場合
1筆の土地を区画分けして売却する場合は宅建業の免許が必要です。
免許を受けずに行えば「無免許営業」となり、宅建業法違反として処罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人は1億円以下の罰金:宅建業法79条)を受ける可能性があります。 - 不動産を購入したら登記は必ず必要ですか?
-
はい。
売買契約だけでは所有権は第三者に対抗できません。
法務局で「所有権移転登記」を行うことで、初めて法的に自分の権利を守ることができます(不動産登記法第4条)。
通常は司法書士に依頼します。 - 不動産を買うと税金はどのようにかかりますか?
-
主に次の税金があります。
・不動産取得税:購入後に1回だけ課税されます(都道府県税)。
・登録免許税:登記の際にかかります。固定資産評価額に税率を乗じて算出。
・固定資産税、都市計画税:毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
・印紙税:売買契約書に貼付する収入印紙代。
- 用途地域とは何ですか?
-
都市計画法に基づき、土地利用を規制するエリア区分です。
エリア毎に、建築可能な建物の種類や規模が制限されます。
例えば、第一種低層住居専用地域では3階建て以上の建物や大規模店舗は建てられません。・住居系(第一種低層住居専用地域など)
・商業系(近隣商業地域、商業地域など)
・工業系(準工業地域、工業専用地域など)
- 宅地造成をする場合、どんな許可が必要ですか?
-
盛土・切土によって高さが2mを超える造成をする場合などは「宅地造成等規制法」に基づく許可が必要です。
また、都市計画区域内で一定規模(例えば3,000㎡以上)の開発を行う場合には「都市計画法の開発許可」が必要になります。
許可なく造成を行うと是正命令や罰則の対象となります。 - 相続した土地を売却するにはどうすればいいですか?
-
まずは相続登記を済ませ、所有者を自分名義に変更する必要があります。
相続登記は2024年4月から義務化されました。
その後、境界確認や測量を行い、必要に応じて土地を整備してから売却活動に移ります。
税金面では「相続税評価額」や「取得費加算の特例」が関わるため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。
資金計画・費用に関すること
- 不動産を購入するとき、物件価格以外にどんな費用がかかりますか?
-
物件価格のほかに「諸費用」が必要です。
一般的には物件価格の7〜10%程度が目安です。
主な内訳は以下の通りです。・登記費用(司法書士報酬、登録免許税)
・ローン関連費用(事務手数料、保証料、火災保険料など)
・仲介手数料
・印紙税(契約書に貼付)
・固定資産税・都市計画税の精算金(売主と日割り計算)
- 住宅ローンを利用する場合、どのような流れになりますか?
-
一般的な流れは以下のとおりです。
このとき、契約書には「ローン特約」をつけることが一般的です。
審査が不承認となった場合、契約を無条件で解除できます。・事前審査:金融機関が借入可能かを確認
・本審査:売買契約後、正式に融資審査を申込
・金銭消費貸借契約(金消契約):融資条件を確認し署名押印
・融資実行・決済:残代金支払いに合わせて実行
- 登録免許税はどのくらいかかりますか?
-
固定資産税評価額に税率をかけて計算します(租税特別措置法による軽減措置あり)。
・所有権移転登記(売買):2.0% → 軽減で0.3%(一定の住宅用家屋に限る)
・抵当権設定登記:0.4% → 軽減で0.1%(住宅ローンの場合)
- 固定資産税はいつから負担するのですか?
-
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます(地方税法343条)。
ただし売買の場合は、売主と買主の間で「引渡日を基準に日割り計算」して精算するのが慣例です。
したがって、購入した年の固定資産税の一部を負担する必要があります。 - 住宅ローン控除とは何ですか?
-
住宅ローンを利用して自宅を購入した場合、年末のローン残高の0.7%を所得税・住民税から控除できる制度です(租税特別措置法41条の2)。
資金計画を立てる際に「控除による節税効果」も考慮することが重要です。・控除期間は原則13年間(新築住宅の場合)
・中古住宅でも条件を満たせば適用可能
- 不動産の仲介手数料は値引きできますか?
-
宅建業法で「上限」が定められており、それを超えて請求することはできません。
一方で、上限以下であれば会社の判断で減額することは可能です。
ただし、多くの場合はサービスの質や責任体制とセットなので、安さだけではなく「信頼できる説明やサポートがあるか」を基準に選ぶことが大切です。 - 不動産を売却すると税金はどのくらいかかりますか?
-
不動産売却時には主に「譲渡所得税」がかかります。
売却価格から取得費(購入時の価格や費用)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた額に課税されます。所有期間5年以下は「短期譲渡」で約39%、5年超は「長期譲渡」で約20%が目安です(所得税+住民税)。
特例控除(3,000万円特別控除など)を利用できれば税額を抑えることも可能です。
物件選び・管理に関すること
- 物件を選ぶとき、どんなポイントを確認すべきですか?
-
主に以下の点が重要です。
・建物の状態:築年数、構造(木造・RC造など)、耐震基準(新耐震=1981年6月以降)
・土地の条件:接道状況、用途地域、建ぺい率・容積率
・生活環境:周辺の交通、学校、商業施設、騒音や日照の状況
・法令制限:市街化調整区域かどうか、再建築の可否など
- 境界や測量はどう確認すればいいですか?
-
境界が不明確な土地は、将来トラブルになりやすいです。
・売買契約前に「確定測量図」があるかを確認することが重要です。
・隣地との立会いによる境界確認が済んでいない場合、引渡し後に越境や境界争いが発覚するリスクがあります。
・必要に応じて、土地家屋調査士へ調査を依頼する必要があります。
- 雨漏りやシロアリ被害など欠陥が心配です。どうすればいいですか?
-
契約前に「建物状況調査(インスペクション)」を利用する方法があります。
・専門の建築士が建物を調査し、劣化や欠陥の有無を報告します。
・中古住宅では、インスペクション済み物件を選ぶと安心度が高まります。
- 空き家を売却する時に注意すべきことは何ですか?
-
空き家は老朽化や越境などのリスクがあるため、事前調査が大切です。
また、一定条件を満たせば「空き家譲渡の3,000万円特別控除」が使える可能性があります。
解体して更地にしてから売る方が買い手が付きやすい場合もあるため、地域の相場や需要を踏まえて判断しましょう。 - 米子市や松江市で土地を売るとき、相場はどうやって調べればいいですか?
-
公的には「公示地価」や「固定資産税評価額」が参考になりますが、実際の売買価格は需給で決まります。
当社では国土交通省の「不動産取引価格情報」や周辺の成約事例をもとに査定し、さらに造成費や地盤の状況なども考慮して適正な価格をご提示します。 - 購入後に欠陥が見つかったらどうなりますか?
-
売主は「契約不適合責任」を負います(民法562条以下)。
・買主は修補・代替物引渡し・損害賠償を請求できます。
・ただし責任期間は契約で定めるのが通常で、中古住宅では数か月〜2年程度に限定されることが多いです。
- マンションを購入すると管理費や修繕積立金が必要と聞きましたが?
-
はい。
区分所有法に基づき、マンションでは以下の費用が発生します。
購入前には「長期修繕計画」や「管理組合の財政状況」を確認することが重要です。・管理費:共用部分(エントランス、エレベーターなど)の維持費
・修繕積立金:将来の大規模修繕に備える積立金